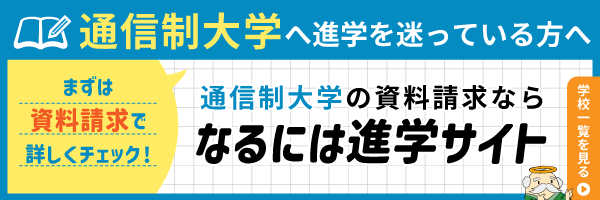社会福祉士とは
社会福祉士は、昭和62年5月の第108回国会において制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格です。
「社会福祉士及び介護福祉士法」には、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又たは 医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされています。
障害を持った方や高齢者の方といった、生活が困難な方やその家族と相談しながら、助言や指導を行います。あくまでも相談援助をする立場で対応するので、直接介護をするわけではありません。別名として「ソーシャルワーカー」や「生活相談員」ということもありますが、この名前の方が馴染みがあるかもしれませんね。福祉施設や行政機関が仕事場ですが、必要ならば医師や介護福祉士、理学療法士、作業療法士、さらにはホームヘルパーとも連携して、相談者の事情に合わせて福祉サービスを提供します。
社会福祉士の資格は国家資格なのですが、医師や弁護士といった「業務独占」資格ではありません。「名称独占」に類する資格です。 つまり、資格を持たない者が勝手に「社会福祉士」という呼び名を使用してはならないという意味です。社会福祉士の資格をもっていなければ、お伝えしたような業務ができないわけではありません。しかし、社会福祉士の資格を持っているということは、専門職としての専門性と高い業務水準を持つ証左となり、今後有資格者が増加することで、将来的には実質的な業務独占状態になるとも考えられています。
国家資格に合格して社会福祉士に!
社会福祉士の国家試験に合格して、はじめて社会福祉士の資格を取得することができます。例えば、介護の相談員として働く場合、資格は特に必要ではありませんが、「社会福祉士」と名乗って仕事をする場合は、国家資格を取得しなければ社会福祉士を名乗ることはできません。お伝えした「名称独占」の資格たる所以、です。
受験資格を得るためには4つのルートが!
社会福祉士となるには、大分して4つの方法があります。
福祉系の4年制大学で所定の課程を修了する
- 福祉系の短大で所定の課程を修了し、実務を1〜2年経験する
- 一般の4年制大学を卒業し、一般養成施設に1年以上通学する
- 一般の短大を卒業し、実務を1〜2年経験し、一般養成施設に1年以上通学する
受験資格を得るためのひとつ目の方法は、福祉系の大学に進んで、4年間の講義を受講する中で、勉強しながら実習を行い卒業することです。この進路の通りだと、大学卒業と同時に社会福祉士国家試験の受験資格を取得することができます。
すぐ上で説明した福祉系の大学でなく、社会福祉系の専門の大学だと、3年間大学でしっかり勉強したあと、1年間の実務経験を積んだ後に受験資格を得ることができます。福祉系の短期大学から資格取得を目指す場合は、2年間の勉強プラス2年の実務経験が必要になり、その後国家資格の受験資格を取得することになります。
この他にも、一般大学へ進学後、一般養成施設で1年以上授業を受講し修了すると受験資格が取得できますが、福祉系の大学や専門の大学、短大のいずれかに進学しておくと非常にスムーズに国家試験の受験資格が得られるのは間違いありません。このように資格取得のルートは複雑で、さらに改正も頻発するので、詳細および最新の情報は各通信制大学にお問い合わせください。
社会福祉士までの道のりをサポートしてくれる通信制大学
社会福祉士は、高齢者や障がい者、生活困窮者など、支援を必要とする人々の相談援助を行う専門職です。国家資格である社会福祉士を取得するためには、福祉系の科目を履修し、国家試験に合格する必要があります。そこで、多くの人が活用しているのが通信制大学です。
通信制大学では、働きながらでも学習を進められる柔軟なカリキュラムが整っています。特に社会福祉士を目指す人に向けたコースがあり、福祉の基礎から実践的なスキルまで学べます。スクーリングやオンライン授業を活用することで、忙しい社会人でも無理なく国家試験の受験資格を得ることが可能です。
また、通信制大学では、社会福祉士試験対策のサポートが充実しており、合格率向上のための特別講座や個別相談も提供されています。福祉の専門知識を身につけ、社会福祉士として活躍するために、通信制大学で学び始めてみませんか?
まずは、各通信制大学に資料請求してみてはいかがでしょうか。