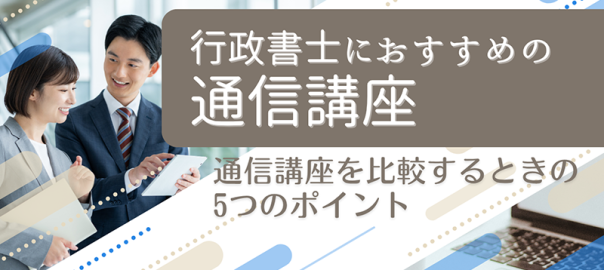行政書士は法律系の国家資格で、年齢や世代問わず受験できることもあり人気があります。行政書士の勉強は予備校に通学する以外にも、独学や通信講座という選択肢があります。
この記事では、行政書士資格・試験の概要を紹介するとともに、おすすめの通信講座についてまとめました。
行政書士は官公庁への書類作成・提出を行う仕事です
行政書士は国家資格であり、官公庁へ提出する許認可申請書類の作成や提出が認められています。
顧客が自分で官公庁への提出書類を作成して提出するのは法律知識が必要であり簡単ではありません。行政手続きの多くは面倒で手間がかかるものであり、書類の不備や記入漏れによって書き直しや再提出が求められれば無駄な時間がかかってしまいます。
行政書士は顧客の代理人として、報酬を得てこれらの手続きを迅速・確実に行えるのです。
行政書士の主な仕事内容は4つです
行政書士の仕事内容をまとめてみました。
| 官公庁に提出する書類の作成と代理 相談業務 |
会社創立の際の許認可申請や相談 例)飲食店営業許可申請、防火対象物使用開始届、深夜における酒類提供飲食店営業開始届 旅客自動車運送事業許可申請、特殊車両通行許可申請など |
|---|---|
| 権利義務に関する書類の作成と代理 相談業務 |
権利や義務の発生、存続、変更、消滅に関する書類の作成や相談 例)遺言書、遺産分割協議書、内容証明、念書、嘆願書、陳述書 |
| 事実証明に関する書類の作成と代理 相談業務 |
社会生活に関わる事項を証明する文書の作成や相談 例)会計帳簿、財務諸表、申述書など |
| その他特定業務 | 社会保険に関わる事務、出入国管理、難民認定に関わる書類の作成 |
行政書士の仕事は幅広く、他にも様々な業務を行うことがあります。
- 自動車ナンバーの変更などの自動車登録手続き
- 中小企業の経営支援
- 著作権の登録申請
- 知的財産権の保護
業務範囲が広い行政書士は許認可申請の専門家として働いたり、ビジネスコンサルタントとして働いたり、予防法務で企業をサポートしたりなど、自分の興味がある分野やキャリアのある分野を専門として働くことができます。
行政書士が働ける場所は行政書士事務所だけではありません
行政書士の働き方としては、主に4つが挙げられます。
- 行政書士事務所で働く
- 独立開業する
- ほかの士業事務所で働く
- 一般企業で働く
それぞれの働き方の特徴をまとめました。
| 行政書士事務所 | ・独立開業を目指すための知識や経験を積める ・求人は多いわけではなく即戦力が求められることが多いため未経験者の採用は厳しい |
|---|---|
| 独立開業 | ・開業時の研修がなくすぐ始められる ・行政書士会員の9割以上が独立開業している ・レンタルオフィスを使えば初期費用を抑えられる ・自宅と事務所とすることもできるが登録要件は厳しい ・得意分野にしぼって営業するのがおすすめ |
| 他の士業事務所 | ・弁護士事務所や社会保険労務士事務所などで働くことができる ・契約書や申請書作成業務など知識を生かして働ける ・弁護士事務所では行政書士の有資格者はパラリーガルとして働くのが一般的 ・得意分野を取り扱う士業事務所を確認するのがおすすめ |
| 一般企業 | ・一般企業の法務部や総務部で働く道もある ・建設や不動産など許認可申請の契約書作成が必要な場合は知識を生かして働ける ・一般企業では「行政書士」として働けないため一般社員として働くことになる |
また、行政書士は他にも暮らしに役立つ様々な相談に応じたり、手続きをしたりすることもできます。
- 成年後見
- 法人関連手続き
- 外国人雇用関係
- 土地活用
- 内容証明
- 中小企業支援
- 運輸関連
- 電子申請・電子調達
そのため、働き方も多種多彩です。
- 自治体などの相談員
- 行政書士会の相談員
- 自治体の各種公的委員会
- 交易認定党委員
- 民事調停員
- 家事調停委員
- 行政改革推進委員
行政書士の資格を持つことは、就職の選択肢を広げることにも繋がります。
行政書士と司法書士の違いをまとめました
行政書士と司法書士がどう違うのか分からないという方がいるかもしれません。行政書士、司法書士はどちらも法律を扱う専門家であり、国家資格です。
しかし、業務内容には大きな違いがあります。
| 行政書士 | 司法書士 | |
|---|---|---|
| 業務概要 | 官公庁に提出する許認可などの 書類作成・手続き代行 |
法務局に提出する登記などの 書類作成・手続き代行 |
| 基づく法律 | 行政書士法 | 司法書士法 |
| 管轄 | 総務省 | 法務省 |
| 主な書類提出先 | 官公庁 | 法務局、裁判所 |
| 仕事内容 | ・書類作成業務 ・手続き代行業務 ・相談業務 |
・登記にまつわる書類作成、手続き代行業務 ・簡易裁判所における訴訟代理人業務(認定司法書士のみ) ・青年後見人、不在者財産管理人業務 ・相談業務 |
| 試験難易度 | 合格率10~13% | 合格率5%前後 |
| 出題範囲 | 憲法、行政法、民法・商法および基礎法学 | 憲法。民法、刑法、商法、不動産登記法 商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法 |
行政書士の作成する書類は官公庁に提出するものや権利義務・事実証明に関する書類で、それらの相談を受けたり提出手続きを代行したりしています。
一方司法書士は不動産登記、商業登記、登記申請書作成や申請の代行をしています。
会社を設立するときを例に挙げると、行政書士は定款の作成や各種許認可申請をしますが、司法書士は設立登記を行うのが仕事です。このように、行政書士と司法書士は業務領域が異なります。
また、試験の難易度は司法書士の方が試験範囲が広く、合格率も低くなっています。
行政書士は今後も需要が見込める資格・職業です
行政書士の仕事である許認可業務は、新しい職業が増えるたびに許認可案件が増えるため需要が減ることはないと考えられます。
また、産廃物の収集運搬・処分業務では複数の許認可が必要になりますが、スムーズに仕事をするためにも関連する許認可取得の提案や実行をするコンサルティング能力があれば他の行政書士と差別化でき、自分の強みとして生かすことができるようになるでしょう。
許認可業務以外では、知的資産も重要となります。中小企業では補助金を得るための支援も増えており、行政書士として「知的資産報告書」作成をサポートするなど今後需要が増えることが考えられます。
行政書士になるための3つの方法を紹介します
行政書士になる方法の1つ目は、行政書士試験を受験して合格することです。ただし、行政書士は試験に合格するだけでは行政書士として活動できません。
- 行政書士試験に合格する
- 事務所の住所を管轄する都道府県の行政書士会に入会する
- 所定の書類を提出して行政書士名簿に登録する
行政書士試験には年齢制限がありませんが、未成年者は試験に合格しても成年に達するまで行政書士になれません。
行政書士になる方法2つ目が、弁護士や弁理士、公認会計士、税理士いずれかの資格を持つことです。これらの資格を持てば、自動的に行政書士の資格も自動的に取得できます。
3つ目の方法は、国や地方自治体の公務員として行政事務を20年以上担当することです。これは特任制度と呼ばれており、条件を満たせば行政書士になる資格を得られるのです。
行政書士になるもっとも一般的な方法は行政書士試験への合格ですが、他にも方法があるということを抑えておきましょう。
特定行政書士になれば弁護士にしかできなかった業務ができる
特定行政書士は、平成27年の改正行政書士法によって創設された制度です。
特定行政書士になると、弁護士にしかできなかった不服申し立て手続きができるようになります。
行政書士は、訴訟手続きはできず、不服申し立て手続きも弁護士の独占業務だったため途中で担当を弁護士に代わる必要がありました。しかし、特定行政書士制度が創設され、同じ担当者が許認可等の申請から不服申し立て手続きまで一貫して代理業務を行えるようになったのです。
特定行政書士ができる不服申し立て手続きはこちらです。
- 審査請求
- 再調査請求
- 再審査請求
特定行政書士になるためには、以下の流れが必要です。
- 特定行政書士法定研修の受講
- 試験
- 特定行政書士登録手続き
研修は全18時間、受講料は8万円となっています。試験は30問の択一式問題となっていて、6割程度が合格ラインと言われています。
行政書士試験は毎年11月の第2日曜日に行われます
行政書士試験の概要を確認しておきましょう。
| 受験資格 | 年齢、性別、学歴関係なく誰でも受験できる |
|---|---|
| 試験科目 | 憲法、行政法、民法、商法、基礎法学、行政書士の業務に関し必要な基礎知識 |
| 合格基準 | 一定の基準を満たせば合格できる「絶対評価」 |
| 出題形式 | 択一式と記述式 |
| 問題数 | 全60問 |
| 受験料 | 10,400円 |
| 受験日 | 11月の第2日曜日 |
行政書士試験のスケジュールはこちらです。
- 7月~8月:願書配布/出願
- 11月:行政書士本試験
- 1月:合格発表
受験申し込みは郵送、インターネットどちらでも行えますが、締切日の設定が違うのでしっかり確認するようにしてください。
行政書士の試験は300点中180点取れれば合格です
行政書士試験は、2つの科目に分かれています。
- 法令等科目:択一式および記述式(40字程度で記述解答)
- 基礎知識科目:択一式
具体的な科目を見てみましょう。
| 法令等 (合計:244点) |
・基礎法学 ・憲法 ・民法 ・行政法(一般的法理論・統合、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法・損失補償、地方自治法、総合問題) ・商法 |
|---|---|
| 基礎知識 (合計:56点) |
・一般知識 ・行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 ・文章理解 |
また、合格基準は試験問題の難易度を見て補正的措置が取られることもあります。
行政書士試験の合格率はおよそ11%です
行政書士試験の合格率は年度によりますがおよそ10~13%で前後しており、平均すると約11%程度となります。
過去5年間の合格率がこちらです。
| 令和元年度 | 11.5% |
|---|---|
| 令和2年度 | 10.7% |
| 令和3年度 | 11.2% |
| 令和4年度 | 12.1% |
| 令和5年度 | 13.98% |
行政書士試験の合格率が高くならないのは、行政書士は資格を持つ人だけができる独占業務があり、社会に対しての責任も問われるため一定の能力が必要となるからです。
むやみに合格者を増やすことがないよう試験の難易度が高くなっていて、合格まで平均で2~3回受験する人が多いと言われています。
行政書士試験に必要な勉強時間は500~800時間ほどです
行政書士試験合格のための勉強時間は毎日しっかりと時間を確保できれば4か月程度でも合格を目指すことができますが、1日2時間の勉強では250日~400日かかるため1年以上の時間が必要となるでしょう。
行政書士と一緒に持つのがおすすめの4つの資格を紹介します
行政書士資格だけでも就職や転職で有利になるのですが、他の資格と一緒に持つことでより仕事選びの幅が広がるようになります。
行政書士と相性の良い4つの資格を紹介します。
司法書士は法務局への書類作成代行業務が行えます
行政書士は役所に提出書類の作成を行うのが仕事ですが、司法書士は法務局へ提出する登記や訴訟に関する書類作成・提出を行います。
司法書士、行政書士どちらの資格も持つことで法務局と役所両方の書類作成に対応できるようになります。
重複する試験科目もあり、勉強しやすいでしょう。
中小企業診断士は会社設立後のサポートができる資格です
中小企業診断士は、経営状況や財務状況を調査したり分析したりできる国家資格です。企業のコンサルティングを行えるため、行政書士資格で会社の設立に関わり、その後は中小企業診断士としてサポートすることができます。
社会保険労務士は人事・労務の専門家です
労働関係、年金、保険関係の専門家である社会保険労務士は、労務管理や労働法に関する書類作成を行っています。
行政書士は設立時に関わるのが仕事ですが、社会保険労務士は経営段階で人事・労務に関わるので2つの資格を持つことで一貫して会社をサポートすることができます。
宅地建物取引士は不動産取引の専門家です
宅地建物取引士(宅建士)は不動産取引の専門家として、重要事項説明をしたり、重要事項書面や契約書に記名したりします。
行政書士の資格とどちらも取得することで、不動産に強い行政書士として専門性の高い仕事ができるようになる可能性があります。
不動産取引に関する法律、制度について相談を受け書類作成をすることができるようになります。
行政書士試験は通信講座で合格が目指せます

行政書士試験は独学でも勉強できます。
独学で勉強すると費用を抑えられ自分のペースで勉強できるメリットはあるのですが、疑問点が出た時に教えてくれる人がいない、法改正に対応できない、モチベーションを維持できないというデメリットもあります。
そこでおすすめなのが通信講座です。
行政書士試験対策に通信講座を使うメリットをまとめました。
- 教材が充実している
- カリキュラムが組まれている
- 自宅や移動中など好きな時に好きな場所で勉強できる
- ネット配信やDVDで講義を受けるので何度でも繰り返して勉強できる
- 専門の講師による講義が受けられる
- 予備校より費用が安い
- 質問対応などのサポートが受けられる
通信講座は独学と同じく自分の都合に合わせて勉強できるだけでなく、ノウハウのつまった教材を使って講義が受けられる、分からないことは質問できるといった独学にはないメリットもあります。
1人で勉強をしようと思っても、進め方や学習計画の立て方でつまずいてしまう可能性があります。
通信講座を利用して、自分のペースで行政書士の勉強を進めていきましょう。
独学、通学予備校、通信講座で行政書士合格を目指すメリット・デメリットを比較しました
行政書士試験の合格を目指すにあたり、勉強する方法は独学、通学予備校、通信講座の3つがあります。
それぞれにメリットやデメリットがあるので比較してみました。
| 独学 | 通学予備校 | 通信講座 | |
|---|---|---|---|
| メリット | ・費用が安い ・自分に合ったテキストを選べる ・自分のペースで勉強できる |
・学習計画が立てやすい ・勉強仲間ができる ・分からないときはすぐに講師質問できる |
・通学するより費用が安い ・好きな時間、好きなペースで勉強できる ・合格実績のある通信講座のノウハウ、カリキュラムで勉強できる |
| デメリット | ・勉強方法、順番が分からずに学習が進まない可能性がある ・誤った理解をしていても指摘してもらえない ・法改正にすぐ対応できない |
・費用が高額になってしまう ・通学する時間が必要で仕事をしている人は難しい |
・費用が独学よりも高額になる ・近く良い予備校がないと通えない ・初めて見るまで自分に教材や講師が合っているか確認しづらい |
独学はすべて自分でスケジュールを立てなければいけないので、強い意志がなければ続けられません。教えてくれる講師もいないのでテキストの情報量が少なければ理解も難しくなるでしょう。
予備校への通学は仲間ができて同じ目標に向かって一緒に勉強できますし分からないところはすぐに質問できる環境にあるのが魅力ですが、どうしても費用が高額になってしまいます。通いやすい場所、時間の予備校がなければ、物理的に通えない人もいるでしょう。
通信講座は、動画講義で時間や場所を選ばずに自分の好きな時間に講義を受けられますし、教室費用などの費用がかからないため通学よりも安く学ぶことができます。質問や返金・お祝い金などのサポートをしている通信講座もあるので、モチベーションにもなりますね。
- 通学する時間がとれない
- 自分のペースで勉強したい
- 確立されたカリキュラムで学びたい
これらに該当する人は、通信講座での勉強がおすすめです。
行政書士通信講座を比較するときは5つのポイントをチェックしよう
たくさんある行政書士通信講座の中から、どれが自分に合っているのかを探さなければいけません。
ここでは、講座を選ぶポイントを6つ紹介します。ぜひ参考にしてください。
ポイント①合格率を見て選ぼう
行政書士試験の合格率は11~13%前後ですが、通信講座の合格率は50%以上であることが珍しくありません。
勉強したことがある人はもちろん、初心者の方も合格率が高い講座を選ぶようにしましょう。
ただし、合格率を公表している講座の中には課題や履修状況などの条件を満たした人だけを対象としていることもあります。
全受講生の中から合格率を算出しているわけではないこともあるので、そこは注意が必要です。
ポイント②自分に合う教材を選ぼう
テキストをチェックするときは、次のポイントを押さえておきましょう。
- 試験範囲を網羅しているか
- わかりやすく説明しているか
資料請求をして実際のテキストサンプルを見ておくとイメージしやすくなります。
テキストは紙ベースだけでなくオンライン上で見るデジタルブックタイプもあります。フルカラーの方が視覚的にも見やすく、より学びやすくなっているのでおすすめです。
ポイント③スマホ学習・音声学習に特化した通信講座を選ぼう
通信講座にはテキストだけでなく動画講座もあります。会社で働きながら合格を目指す社会人の場合、空き時間に勉強しやすいようにスマホ学習や音声学習に強い通信講座を選ぶのも良いでしょう。
動画講座については、次のポイントをチェックしたいですね。
- 動画講座だけでなく音声講座もある
- ダウンロードしてオフラインでも見たり聴いたりすることができる
- 倍速視聴ができる
この3点が可能だと、移動中などに確認しやすくなります。
また、スマホでできる機能がたくさんあるのも便利です。
- 過去問集
- 一問一答
- 模擬試験
- 質問
- 学習計画作成、提案
通信講座を選ぶときは、スマホやタブレットで出来ることを比較するのもおすすめです。
ポイント④無料体験講座を受けて選ぼう
合格率が高くテキストの内容がよさそうでも、実際に受講してみると「合わないかも…」と感じてしまうことはあります。そこでおすすめなのが、無料体験講座を受講することです。
実際の講義動画を見る、テキストを見ることで、自分に合うかどうかが判断しやすくなります。
講師の雰囲気、自分との相性が分かるので、講座選びの参考になるでしょう。
ポイント⑤合格得点やサポート体制が充実しているものを選ぼう
初心者は特に法律用語などが難しく理解しにくいことで挫折してしまうことがあります。せっかくの学習を無理なく続けられるように、サポート体制が充実しているところを選んでください。
- 質問制度がある(回数制限があるかどうかも要確認)
- 記述式問題対策がある
- 返金制度がある
- お祝い金制度がある
勉強効率を高めるためには正しい知識を正しく理解することが大切です。なんかわからないことがあったとき、自分で間違った解釈をしないように講師に直接質問できることは大切です。
質問制度については回数制限があるものやチケットを購入するものがありますので、質問できる条件について確認しておきましょう。
行政書士試験には記述式問題があります。自分の解答を添削してもらい適切にフィードバックしてもらうことで、客観的に自分に不足している部分を確認することができます。
返金制度は、合格時・不合格時など、講座によって返金条件が異なります。講座費用は安くありませんから、返金制度があると嬉しいですよね。
合格すると一定額がもらえるお祝い金制度を設けている講座もあります。合格を目指すモチベーションの1つにもなるので、ぜひチェックしておきましょう。
ポイント⑥予算に合う料金の講座を選ぼう
行政書士講座の費用は5万円~25万円程度と幅広くなっています。自分の予算に応じて講座を選ぶことも大切ですが、費用が安くても試験範囲のカバー率が悪かったりテキストが分かりにくかったりするとお金がもったいないですよね。
費用が安い、というだけで選ぶのではなく、教材やサポート内容をしっかり見てから選ぶようにしましょう。
受講料が少し高いなと感じても、サポートがしっかりしていて教材の内容が充実している講座を選ぶと効率のよい勉強ができるでしょう。
費用を抑えたいのであれば、各種割引サービスがあるかどうかを確認するのも良いでしょう。
- 早期申し込み割引
- 再受講割引
- 他資格試験合格者割引
- 他校乗り換え割引
また、教育訓練給付金を受給できる場合もあります。
教育訓練給付金は、講座費用の20%(最大で10万円まで)をキャッシュバックしてもらえる制度です。
利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 国が指定した講座を受講して修了した
- 受講開始日時点に在職中で雇用保険に加入している
または離職して1年以内である - 今まで一度も教育訓練給付金を受けたことがなく
雇用保険加入期間が1年以上ある - 以前に教育訓練給付を受けたことがあるが
前回の受講開始日校雇用保険加入期間が3年以上ある
また、教育訓練給付制度は受講料のみが対象となっているので、交通費やパソコンの費用、クレジット払いの手数料などは対象外です。
教育訓練給付制度が利用できる講座と利用できない講座があるので申し込み前に確認しておきましょう。
おすすめの行政書士通信講座を比較して紹介します
たくさんある行政書士講座の中から、おすすめの講座を5つピックアップして紹介します。
| アガルート | キャリカレ | スタディング | フォーサイト | 伊藤塾 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格実績 | 令和5年度56.11% | 公式サイトに記載なし | 2023年度合格者216名 | 2023年度の45.45% | 2024年度合格者359名 |
| 受講期間目安 | 15ヵ月~17ヶ月 | 4か月~ | 12か月~ | 4か月~ | 6か月~ |
| 費用 | キックオフ48:43,780円~(税込) | サポート期間1年:73,800円(税込)~ | ミニマム:34,980円~(税込) | バリューセット1:66,800円~(税込) | スタンダードコース:218,000円~(税込) |
| サポート体制 | オンライン質問サービス バーチャル校舎 各種割引制度 |
不合格時に全額返金 合格で別講座受講が1つ無料 |
AIサポート機能 勉強仲間機能 |
eラーニングシステム 全額返金保証制度 |
個別質問 個別カウンセリング制度 オンライン質問会 |
| 特典・キャンペーン | 各種割引 合格時全額返金 |
春割キャンぺ―ン | Wライセンス応援割 更新割引 合格お祝い金 |
合格お祝い金Amazonギフト券2,000円 | 早期割引 期間限定特別割引 学割 |
| 教育訓練給付制度 | - | - | - | 対象 | - |
それぞれの通信講座について詳しく見ていきます。
レベル別講義で初心者でも行政書士通信講座が学べる【アガルート】
アガルートは行政書士の通信講座の中でも知名度が高く、高い合格率を誇ります。令和5年度の行政書士試験では合格者が304名となりその中の171名が一発合格しています。
- 初級から上級までレベルに合わせた講座が受けられる
- テキストは出題カバー率が95.65%で必要な知識を網羅できる
- サポート体制が整っていて無理なく学習できる
- キャンペーンが豊富でお得に学べる
- 合格すると全額返金されるサービスがあるのでモチベーションが上がる
- 動画は音声ダウンロードが可能で8段階の倍速再生もできる
教えるのは合格者から指示を得ている実績のあるプロ講師で、何か受講について不安なことがあれば専門スタッフが対応するなど勉強内容だけでなくサポート体制も充実しています。
また、アガルートは入門から中上級向け、上級向けのレベル別講座を用意しています。
| 対象 | コース | 費用 |
|---|---|---|
| 初心者向け | 行政書士キックオフ48 入門総合カリキュラムライト 入門総合カリキュラムフル 入門総合講義 |
43,780円(税込) 205,920円(税込) 295,020円(税込) 166,320円(税込) |
| 経験者向け(中上級) | 中上級総合講義 中上級総合カリキュラムライト 中上級総合カリキュラムフル |
245,520円(税込) 285,120円(税込) 374,220円(税込) |
| 経験者向け(上級) | 上級総合カリキュラムライト 上級総合カリキュラムフル |
196,020円(税込) 285,120円(税込) |
自分のレベルに応じた講座やカリキュラムを選ぶことができます。
資料請求をすればフルカラーテキスト、一部講義動画。オンライン演習サービスが無料で利用できるので、興味がある方は試してみると良いでしょう。
| 合格実績 | 令和5年度56.11% |
|---|---|
| 費用 | キックオフ48:43,780円(税込)~ |
| 教材 | 製本、デジタルブック 動画は8倍速で視聴可能 |
| サポート体制 | バーチャル校舎 オンライン質問サービスKIKERUKUN (カリキュラムにより20~50回質問できる) 各種割引制度(他校乗り換えや受験権威検車割引など) |
| 合格特典 | 全額返金もしくはAmazonギフト券万円分 |
| 教育訓練給付制度 | - |
- 費用が高くてもノウハウのある教材で一発合格を目指したい人
- サポート体制が充実している通信講座を利用したい人
- 法律の勉強が始めてで、経験豊富な講師から学びたい人
- 合格特典の全額返金を狙いたい人
120日で資格取得を目指す【キャリカレ】
キャリカレは1日60分、4か月で合格を目指すコースがある通信講座です。
- 試験に出るところだけを集中して学ぶので短期間で合格を目指せる
- サポート期間なら質問は何度でも無料で対応してもらえる
- 不合格でも全額返金保証サポートがある
- 行政書士合格で社会保険労務士講座が無料受講できる
- 転職サポートや開業時のホームページ作成サポートサービスがある
通常1~2年ほどの勉強時間が必要な行政書士対策ですが、試験に出るところだけを学ぶことで短期間での合格を目指すことができます。キャリカレは試験対策用の過去問も準備していて、重要問題だけを分野別に学ぶことができます。
キャリカレの行政書士講座はサポート期間の違いで3つのコースに分かれています。
| サポート期間1年2カ月 | 83,800円(税込) |
|---|---|
| サポート期間1年1カ月 | 78,800円(税込) |
| サポート期間1年 | 73,800円(税込) |
教材内容はすべて同じです。テキストや映像教材、条文集、過去問集、添削問題集が含まれています。
| 合格実績 | 公式サイトに記載なし |
|---|---|
| 費用 | 73,800円(税込)~ |
| 教材 | 紙、WEB |
| サポート体制 | 不合格時に全額返金 合格すると別講座1つの受講料が無料 |
| 教育訓練給付制度 | - |
キャリカレは不合格での返金制度があることから、講座内容に自信を持っていることが分かります。合格するとキャリカレの講座を1つ無料で受講できるので、ダブルライセンスを希望する人にもおすすめです。
- 短期間での合格を目指したい人
- 資格取得後もフォローを希望する人
- 行政書士と合わせて社会保険労務士や宅地建物取引士の資格取得を目指す方
行政書士通信講座の費用が安い【スタディング】
スタディングの行政書士講座はWEB講義やWEBテキストでコストをカットすることで他社と比較して安く学習することができます。WEBで学べるため、スマホやタブレットでの勉強に適していますね。
- 受講指導20年以上の講師が行う講義動画
- 初学者でもわかりやすい図や具体例を使った動きのある動画
- 今までのノウハウによる効率的に学べるカリキュラム
- AIが理解度に合わせて復習スケジュールを設定
- 学習Q&Aチケットを使えば疑問・質問を行使が答えてくれる
学習はすべてスマホで行えるため、通勤・通学中、ちょっとした空き時間に勉強できます。1つの動画がおよそ5分からというのも見やすいでしょう。音声のみのダウンロードにも対応していますよ。
| 概要 | 費用 | |
|---|---|---|
| ミニマム | 基本講座・WEBテキスト | 34,980円(税込) |
| スタンダード | ミニマム+一問一答・過去問、記述式講座・問題集 | 54,000円(税込) |
| コンプリート | スタンダード+横断総まとめ・答練、Q&Aチケット30枚 | 69,400円(税込) |
スタディングはITを活用した学習システムでコストを削減することにより、他社と比較して始めやすい価格になっています。
ビデオ講座、フルカラーWEBテキスト、スマホで解ける問題集を無料で試すこともできます。興味がある方はぜひ申し込んでみてください。
| 合格実績 | 2023年度216名 |
|---|---|
| 費用 | ミニマム34,980円~ |
| 教材 | 動画講義(音声のみのダウンロード可) WEBテキスト 紙のフルカラーテキストもある |
| サポート体制 | 勉強仲間機能 AIサポート機能 |
| 教育訓練給付制度 | - |
スタディングでは同じ資格を目指す仲間を作る勉強仲間機能があり、学習を続けるモチベーションを維持することができます。
今日は何を勉強しよう、と悩まないように最適な学習順を教えてくれる学習フロー機能もあり、効率よく学ぶことができます。
- とにかく費用を抑えて勉強したい人
- テキストは紙ではなくWEBだけでも十分な人
- 隙間時間で効率よく勉強したい人
ライフスタイルに合わせた学習計画を自動で設定してくれる【フォーサイト】
フォーサイトは初めて勉強する人でも迷わないように、eラーニング「ManaBun」で生活に合わせた学習スケジュールを自動で立ててくれます。スケジュールに沿った学習進捗管理も可能です。
- 合格点主義で短期間での合格を目指すこともできる
- 紙のフルカラーテキストと利便性の高いデジタルテキストを併用できる
- 受講者数が累計8万人を超え、多くの人が利用している
- 教育訓練給付制度が利用できる
- 不合格時の全額返金保証制度がある
フォーサイトの講義動画は最大で1つ15分以内と隙間時間に確認することができます。また、eラーニングシステムはスマホやパソコン、タブレットで学習でき、講義データを事前にダウンロードしておくことで通信環境を気にせず視聴できます。
| 概要 | 費用 | |
|---|---|---|
| バリューセット1 | 基礎講座、過去問講座 | 66,800円(税込) |
| バリューセット2 | セット1+直前対策講座 | 76,800円(税込) |
| バリューセット3 | セット2+ペースメーカー答練講座、過去問一問一答演習 | 94,800円(税込) ※DVDオプションで99,800円(税込) |
バリューセット1~3はいずれも教育訓練給付制度の対象となっていますが、全額返金保証制度が利用できるのはバリューセット3だけです。
| 合格実績 | 2023年度45.45% (バリューセット3受講生) |
|---|---|
| 費用 | バリューセット1:66,800円~(税込) |
| 教材 | eラーニング (ダウンロード、連続再生、倍速再生可能) 紙のテキスト |
| サポート体制 | eラーニングシステム 全額返金保証制度 |
| 教育訓練給付制度 | 対象 |
教育訓練給付制度を利用できるので、条件をクリアすれば受講料の20%が給付してもらえる可能性があります。
- コスパよく通信講座を利用したい人
- 最短4か月での合格を目指したい人
- 自分に合う学習計画を自動で立ててほしい人
法律系資格に特化している【伊藤塾】
伊藤塾は司法試験、司法書士試験、公務員試験、行政書士試験、海事代理士試験など法律系試験に特化しており、1995年の開塾依頼多くの法律家や行政官を輩出しています。
- 法律専門の指導校で業界TOPレベルの講師の指導が受けられる
- 一発合格や短期合格を目指している講座もある
- 講師による直接指導や個別質問制度などフォロー体制がある
- 定期的なカウンセリングで一緒に学習スケジュールを立て、進捗確認ができる
- 合格後には「秋桜会」という同窓会に入会でき、同業の人とのつながりが作れる
司法試験塾としてスタートしており、法律系資格に特化しているのでクオリティの高い教材を開発、使用しています。
伊藤塾では豊富なコースを用意しており、自分に合ったものを選べます。
| コース | 費用 | |
|---|---|---|
| 初学者向け | スタンダードコース 速修コース コンプリートコース |
238,000円(税込) 188,000円(税込) 268,000円(税込) |
| 中上級者向け | アドバンスコース 上級コース ブラッシュアップ100 |
238,000円(税込) 248,000円(税込) 198,000円(税込) |
受講料は他の通信講座と比べても高めですが、コースによってオンライン質問会やスクーリング、パーソナルトレーナー制度などサポート体制が充実しています。
| 合格実績 | 2024年度合格報告359人 |
|---|---|
| 費用 | スタンダードコース218,000円~(税込) |
| 教材 | 白黒テキスト |
| サポート体制 | 個別質問制度 個別カウンセリング制度 スクーリング制度 オンライン質問会 早期割引 期間限定特別割引 学割 |
| 教育訓練給付制度 | - |
伊藤塾のテキストは白黒ですが教材開発に力を入れており、重要科目である民法や行政法を重視しています。
- 法律を専門としたハイレベルな講師の指導が受けたい人
- 通塾も見据えて勉強したい人
- 手厚いサポートを希望する人
行政書士の通信講座によるある質問をまとめました
行政書士試験対策のために通信講座を選ぶにあたってよくある質問や不安をまとめました。
行政書士試験は誰でも受験できますか?
行政書士の試験を受ける条件は特にありません。年齢、学歴問わず受験することができます。
ただし、未成年者は合格しても成年に達するまで行政書士にはなれません。
行政書士試験の内容について知りたいです
行政書士の試験は、法令等科目と基礎知識科目の2科目です。
- 法令等科目:択一式および記述式(40字程度で記述解答)
- 基礎知識科目:択一式
法令等科目では満点の50%以上、基礎知識科目では満点の40%以上を得点した上で、試験全体の得点が満点の60%以上であることが合格基準です。
行政書士試験は記述式問題もあり、300点満点中60点を占めています。分からなくても部分点がもらえるので、必ず書くようにしなければいけません。
記述式問題を落とさないことが合格のポイントとなるでしょう。
行政書士試験の難易度を教えてください
行政書士試験の合格率は10~13%程度と決して簡単ではありません。行政書士試験は範囲が広く科目ごとに合格基準点があるので、1つの科目で基準点をクリアしても合格できないのです。
ただし、行政書士試験は絶対評価制となっていて基準点をクリアすれば合格できます。合格までの平均受験回数は2~3回となっていて、合格まで2~3年かかるケースが多いですね。
ちなみに、宅建士の合格率は約15%、社労士の合格率はおよそ7%ですから、宅建士よりは難しく社労士よりは簡単な試験と言えます。
行政書士試験の勉強はどのくらい必要ですか?
勉強時間は500~800時間ほど必要だと言われていますが、法律を初めて学ぶ場合は1,000時間ほど必要になってきます。
1年間で800時間の勉強量を確保するためには、1日2時間程度勉強する必要があります。
本年度中に合格したい場合は5月頃までには講座に申し込みをして、来年度の合格を目指す人も早めに通信講座を申し込むと良いでしょう。
行政書士試験は通信講座でも勉強できますか?
行政書士試験は通学、独学、通信講座で勉強して合格を目指すことができます。
ただし、通学はしっかりカリキュラムに沿って講師から学べるメリットがありますが費用が高額になりますし、独学は費用は抑えられても誤った認識をしていても教えてくれる人がいませんし法改正などの最新情報に対応できない、モチベーションが維持できないなどのデメリットがあります。
一方、通信講座は合格実績のあるカリキュラムで勉強できますし、疑問点は質問できたりオンライン教材で隙間時間に学べたりできます。費用も通学より抑えられますので、働きながら合格を目指したい人におすすめです。
行政書士講座はどのくらい費用がかかりますか?
費用目安は、5万円~30万円程度です。コースの内容やオプションによっても費用は変動します。
早期割引や教育訓練給付制度を活用すれば、お得に受講することもできます。
1人で勉強を続ける自信がありません
通信講座には、質問対応をしてくれるサポートや、同じ講座を受講している仲間と交流できるサービスを行っているものがあります。
1人で勉強をしているのではなく仲間がいる、講師の先生が一緒に学習してくれると思えれば勉強を続けられるでしょう。
通信講座を選ぶときにサポート内容を確認して選ぶと良いですね。
法律を学ぶのは初めてですが大丈夫でしょうか
行政書士試験は法律について勉強する必要がありますが、初心者向けに基礎から学べるコースを用意している講座もあるので、そちらを選ぶと良いでしょう。
初学者用のコースでは初歩から段階的に学習が進んでいるため無理なく勉強をすることができますよ。
行政書士通信講座は自分と相性が良くレベルが合うところを探すことが大切です
行政書士の通信講座は、プロ講師の指導が自宅にいながら受けられるものです。今までのノウハウが詰まった教材、カリキュラムとサポートにより独学よりも効率よく学ぶことができます。
通信講座を選ぶときは合格実績や費用、サポート内容などを比較するようにしましょう。講座によっては教育訓練給付金制度が利用できたりお祝い金制度や返金制度があったりしますから、細かくチェックしてみてくださいね。
同じ会社の通信講座でも複数のコースを用意していることもあります。自分に合ったペースで無理なく続けられるものを選んでください。