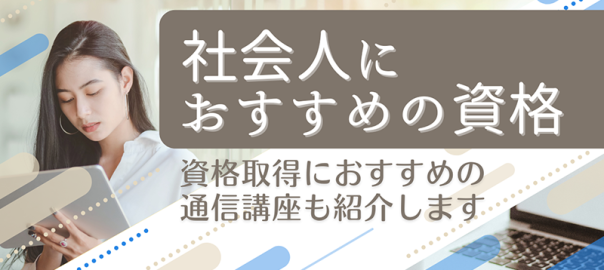社会人として働きながら資格を取得するのは大変ですが、「資格がほしい」「挑戦したい!」という人は多いかと思います。
資格を取ることで、自分に自信がつくのはもちろん、キャリアアップや収入アップが期待でき、一生使える資格なら独立や開業も目指せます。
しかし、資格と一口に言っても、世の中には数多くの資格が存在します。「どの資格を取得すればいいのかな」と迷っている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、社会人におすすめの資格、社会人が資格を取得するメリットやポイント、おすすめの通信講座などを紹介します。
働きながら取得できる!社会人におすすめの資格27選
資格を取るなら、時代のニーズに合った需要のある資格やキャリアアップにつながる資格がおすすめです。汎用性や専門性の高さも重要なポイントです。
難易度の高いものも含め、社会人におすすめの資格を27種類紹介します。
【社会保険労務士(社労士)】難易度は高いけれど独立開業もできる
社労士とは、企業の法令遵守や労働者の権利保護をサポートする国家資格です。
行政機関に提出する書類を法令に基づいて作成・提出代行したり、就業規則や賃金台帳といった帳簿書類を作成したり、社会保険や労務に関するコンサルティング業務を行ったりします。
法律に関する基礎知識はもちろん、社会保険の手続きや企業の労務管理に関する専門的な知識が不可欠です。資格取得後は、社労士事務所で勤務できる以外に、企業内社労士として人事部門や労務部門に勤務することもできます。
社労士は資格を取得した人しか名乗れず、社労士にしかできない独占業務もあるので、実務経験を積んだのちに独立開業を目指せる資格です。
受験資格があるので、満たしているかどうか確認しておきましょう。
【行政書士】難易度は高いけれど、幅広い分野で活躍できる
行政書士は、個人または企業が、官公庁に許認可を取りたいときの法的手続きをサポートする国家資格です。
官公庁に提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類など幅広い分野の書類作成・提出を代行したり、手続きの相談に応じたりします。
法的なトラブルを発生させないために、また、発生したときは速やかに解決するために、予防法務のスペシャリストとして、不動産業界、建設業界、医療業界など幅広い分野で活躍できます。
行政書士には受験資格がなく、誰でも挑戦できるのが特徴です。資格を取得し、日本行政書士会に登録後は、行政書士事務所や一般企業の企業内行政書士として勤務できる他、独立開業を目指せます。
社労士や行政書士はこのように非常に魅力的な資格ですが、難易度が低くないため独学での合格は非常に難しいとされています。
通信講座なら、要点をおさえたわかりやすいテキスト、講義動画に加え、スマホ学習アプリなどもあるので、忙しい社会人におすすめです。

中でも「アガルートアカデミー」なら、難易度の高い資格から低い資格まで豊富に取り扱っており、どれも高い合格実績を誇っています。行政書士、社労士、宅建士など国家資格の講座が多くあり、累計会員登録者数はなんと22万人を突破しています。
講師に質問ができるなどフォロー制度も充実しており、お祝い金もらえたり受講料が全額返金されたりする資格もありますよ。
【宅地建物取引士(宅建士)】受験者数が多い人気の資格!不動産業界で重宝される
宅建士は、不動産売買や賃貸の重要事項の説明や署名・押印、契約書の作成や交付など、不動産取引をサポートする国家資格です。
不動産業の経営には、従業員5人に対し1人以上の割合で宅建士の配置が義務付けられているので、不動産業界では特に重宝される資格です。
宅建士の受験者数は例年20万人以上と人気で、受験資格はないので誰でも挑戦しやすいのが特徴です。
【日商簿記】転職やキャリアアップに活かせる2級以上を目指そう
日商簿記検定は、経理や会計で役立つのはもちろん、金融、事務、営業などの職種でも役立ちます。企業の経理部門、会計事務所、税理士事務所などでは特に資格を活かせるでしょう。
簿記とは、企業のお金の出入りを帳簿に記録し、報告書を作成する作業です。経理に関する実務で使えるスキル、経営分析の基礎知識などが身に付きます。
日商簿記検定には初級・3級・2級・1級がありますが、2級以上を持っていれば、転職やキャリアアップに活かせます。
受験資格はなく、希望する級から受験でき、同日にダブル受験することもできます。
【ファイナンシャルプランナー(FP)】プライベートでも役立つ知識を得られる
FPとは、金融に関する幅広い分野についてアドバイスをしたり、ライフプランを設計したりするお金の専門家です。FPは知名度が高く、金融業界、保険業界、不動産業界では特に資格を活かせます。
貯金、保険、税金、年金、住宅ローン、教育資金、資産運用などの知識を得られ、プライベートでも役立つので、取っておいて損はないでしょう。
国家資格の「FP技能士」がスタンダードですが、日本FP協会が実施している民間資格の「AFP」や「CFP®」も価値のある資格で、ダブル受験する人も少なくありません。
FP技能士には3級・2級・1級がありますが、転職に有利となるのは2級以上です。1級には受験資格があるので、2級に挑戦するのがおすすめです。ただし、2級にも受験資格があり、3級合格か2年以上の実務経験が必要です。
【マンション管理士・管理業務主任者】ダブルライセンスも狙える
マンション管理士は、マンション管理の専門家としてマンションの維持や管理を行い、管理業務主任者は、マンションの管理組合と業務委託契約を結ぶ際に重要事項の説明や事務報告を行う人です。
近年は高経年マンションが増え、修繕や建て替えの必要性が高まっていることから、今後も高いニーズのある資格といえます。
どちらもマンションの管理に不可欠な2大国家資格で、受験資格はありません。共通する出題分野が多いので、一度に両方を受験してダブルライセンスを取得することも可能です。
どちらか1つを選ぶなら、独占業務のある管理業務主任者がおすすめですが、両方取得すれば生涯有効です。年齢を問わず活躍できるので、転職はもちろん定年後の再就職にも活かせるでしょう。
【中小企業診断士】男性に人気の資格で、業種や職種を問わず重宝される
中小企業診断士は、「日本版MBA」ともいわれる、経営コンサルタントの代表的な国家資格です。
日本の企業は、9割以上を中小企業が占めています。中小企業が抱える経営課題を解決へと導き、成長を支えて促すのが中小企業診断士の仕事ですが、企業数は多いものの中小企業診断士の数はまだまだ少ないのが現状です。
業種や職種を問わず重宝される資格なので、転職の際も好条件で採用される可能性が高いです。経営に精通したエキスパートとして、独立開業も目指せます。
男性に人気のある資格で、特に30~40代の受験者が多い傾向です。一次試験と二次試験があり、難易度は高いですが、受験資格はないので誰でも挑戦できます。
【危険物取扱者】幅広い業界で即戦力として評価されやすい
危険物取扱者は、ガソリン、石油、引火性物質などの危険物を正しく取り扱う国家資格です。危険物は取り扱い方法を間違えると火災につながる恐れがあるので、資格を持った人しか大量に製造・貯蔵・取扱ができないようになっています。
ガソリンスタンド、化学工場、印刷関係の会社、燃料や塗料関係の会社など幅広い業界で活躍でき、転職の際は即戦力として評価されるでしょう。
危険物取扱者試験は、扱える危険物の種類によって甲種・乙種・丙種の3種類に分かれ、乙種はさらに6種類に分かれます。転職を考えている場合は必要とされる資格を確認しておく必要があります。
乙種と丙種は受験資格がなく、国家資格でありながら難易度も比較的低いので、誰でも挑戦できます。東京ではほぼ毎月試験が実施され、他の地域でも年に2回は実施されているので、チャンスが多いのも特徴です。
【第二種電気工事士】電気工事関連の会社だけでなく、幅広い業界で資格を活かせる
電気工事士は、建物への電線の引き込み、コンセントの配置や増設、接地工事(アース施工)などを行う専門職です。第二種電気工事士は、電機設備を取り扱う際や電気工事をする際に必要となる国家資格です。
電気工事会社、設備管理会社、建設会社、鉄道工事会社などで需要が高く、ビルメンテナンス、家電販売店、メーカー営業などでも評価されることがあります。
電気なしでは成り立たない時代なので、電気工事士は社会に不可欠な存在です。一度取得すれば生涯有効で、独立開業の道もあります。
第一種と第二種がありますが、第二種は受験資格がないので誰でも受験でき、国家資格でありながら難易度は比較的低いです。実技試験もありますが、通信講座なら必要な練習工具が付属しているものもあり効率よく勉強できます。
【ITパスポート(iパス)】ITの基礎知識を証明できる
iパスは、ITに関する基礎知識を証明できる国家資格です。受験資格はなく、社会人はもちろん、これから社会人になる学生にも支持されている人気の資格です。
ITは、文系・理系、事務系・技術系を問わず、どのような業種・職種にも不可欠になってきています。ITの高度化はますます加速しており、「IT力」を持つ人材を求める企業は増えています。
試験では、ネットワークやセキュリティの知識、AIやIoTといった新しい技術に加え、経営戦略やマーケティング、プロジェクトマネジメントに関する知識なども問われます。
国家資格の中では難易度が低めで、情報処理の知識を持っていれば100時間程度の勉強で合格できるとされています。
試験はPCを利用して各地のテストセンターで実施されるCBT方式なので、年間を通して随時行われています。好きなタイミングで受けられるのが特徴です。
iパス取得後は、上位資格の「基本情報技術者試験」、さらに上位資格の「応用情報技術者試験」に挑戦することで、ITエンジニアやセキュリティ専門家などを目指せます。
【基本情報技術者試験(FE)】DX推進に不可欠な資格で、ITエンジニアとして働く第一歩になる
iパスの次のステップとなる基本情報技術者試験は、ITエンジニアの第一歩となる国家資格です。「ITスキルの登竜門」として知られ、略号でFEとも呼ばれます。
ITの基礎知識や技能に加えて、プログラミングやデータベース、セキュリティ、マーケティング、マネジメントなど主に技術面が問われる試験です。
IT業界のみならず、さまざまな業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)に欠かせない資格です。
基本情報技術者試験は「基本」という名がついているとおり情報技術の基礎を身につけられる試験です。ITエンジニアを目指すなら、しっかりと基礎を身につけることによって、その後の応用力が格段にアップします。
【応用技術者試験(AP)】ITのさらに高度な知識・技能を証明できる
応用情報技術者試験は、基本情報技術者試験の次のステップとなる、ワンランク上のITエンジニア向けの国家資格です。略号でAPとも呼ばれます。
受験資格はないですが、試験の対象となるのは、高度IT人材になるために必要とされる応用的な知識・技能を持っている人です。
ITを活用した製品やサービス、システムなどを作る、高度IT人材としての方向性を確立した人におすすめの資格です。
試験は、テクノロジ系、マネジメント系、ストラテジ系という3つの分野から出題されます。これは、基本情報技術者試験でも同じですが、応用情報技術者試験の方がより深い知識を問われます。
試験は年に2回、指定の会場で実施されます。午前と午後それぞれ150分ずつ行われ、選択式と記述式の問題があります。難易度は高いですが、取得すればITエンジニアとしてスキルアップできるのはもちろん、転職の際にも有利です。
【G検定・E資格】AI時代に不可欠な資格!未経験ならG検定、エンジニアならE資格を取得しよう
G検定(ジェネラリスト検定)と、E資格(エンジニア資格)は、どちらも日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する、AI(人工知能)に関する資格です。
G検定もE資格も、DXの推進に伴い需要が高まっているため、今後のキャリア形成に役立ちます。AIの技術は急速に発展していますが、それを扱えるAI人材は不足しているのが現状です。
G検定では、AIやディープラーニングの活用に必要な幅広い知識を初歩的な部分から体系的に学び、習得できます。AIで何ができるのか・何ができないのか、AIを何に活用すればよいか・活用するためには何が必要かといった知識が身につきます。
G検定はビジネスマン全般を対象とした試験で、AI初心者でも合格を目指せます。
一方、E資格では、AIやディープラーニングを生み出すために必要な知識やスキルを学び、習得できます。取得すれば、AIのスペシャリストとしてさまざまな業界で活躍できるでしょう。
E資格はプログラミングができるエンジニアを対象とした試験で、難易度が高いです。
ちなみに、 AI関連の資格にはAI実装検定(B級、A級、S級)もありますが、難易度的には「AI実装検定B級→G検定→AI実装検定A級→E資格→AI実装検定S級」となっています。
未経験からAIを学びたい方であればG検定、AIエンジニアとしてスキルアップしたい人にはE資格がおすすめです。
【マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)】事務だけでなく幅広い職種で役立つ
MOSは、マイクロソフト社の製品(Excel、Word、PowerPoint、Access、Outlook)の操作スキルを証明できる資格です。
即戦力として認識されやすく、特に一般事務や営業事務の仕事で活かせる資格ですが、職種に関係なくパソコンを扱う社会人なら取っておきたい資格です。
MOSには、一般レベルと上級レベル(エキスパート)の2つがあり、エキスパートの方が難易度が高いです。どちらも受験資格はないので誰でも挑戦できます。
5つすべて取得しなくても、Excel、Word、PowerPointの3つを取得していれば、十分アピール材料になるでしょう。
【TOEIC】ハイスコアをとれば、キャリアアップに有利になる
TOEICは英語のコミュニケーションスキルを証明できる、世界共通の試験です。採用の条件として「TOEIC○○○点以上」を掲げている企業も多く、ハイスコアを獲得すれば、キャリアアップや転職に有利です。
TOEICの試験は、リスニングとリーディングの2つで構成されており、日常会話とビジネス会話が中心です。誰でも受験でき、合否があるわけではなく、点数によって英語力が評価されます。
語学を学ぶときは、毎日の継続が重要となるので、自分に合った英語教材を使いながらコツコツを努力を積み重ねていく必要があります。
英語の学習から遠のいている人でも、基礎から積み上げていき、挫折せずに勉強を続ければ、着実にスコアアップするでしょう。
【TOEFL】海外留学を考えている人におすすめ
英語の代表的な資格には、TOEICの他にTOEFLもあります。どちらも認知度も高く、社内でのスキルアップや転職などに十分に活用できる資格です。
何が違うのかというと、TOEICは国内で就職・転職する際にスコアをチェックされることが多いのに対し、TOEFLは海外留学する際にチェックされることが多い点です。
しかし、TOEICが海外留学する際に役に立たない、TOEFLが就職や転職に使えない、というわけではありません。
また、TOEICの試験はリスニングとリーディングから構成されていますが、TOEFLの試験は読む・聞く・書く・話すの4つから構成されているので、4技能をまんべんなく勉強する必要があります。
海外留学を考えている社会人は、入学にあたって重視されやすいTOEFLを受けておくのがおすすめです。
【IELTS】対面式のスピーキングテストがあり、海外留学を目指す人におすすめ
IELTS(アイエルツ)はここ数年でに日本でも受験者数が急増している、英語力を測る試験です。TOEFLと同じく、読む・聞く・書く・話すの4つから構成されています。
イギリス、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドなど英語圏への留学や勤務、移住の際に重視され、英語力を証明できるグローバルなテストとして世界中で人気が高まっています。
TOEFLはアメリカ発祥の試験ですが、IELTSはイギリス発祥の試験です。TOEFLはアメリカ英語が基本、IELTSはイギリス英語が基本なので、リスニングで発音に違いがみられたり、スペリングの違う単語や言い回しの違う表現があったりします。
以前はアメリカに留学するならTOEFL、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドに留学するならIELTSという認識でしたが、現在はアメリカでも多くの教育機関がTOEFLに代わる試験としてIELTSを取り入れています。
IELTSのスピーキングテストは、面接官との対面式で行われ、自然に話す力を試されるのが特徴です。TOEFLにもスピーキングテストはありますが、PCに話しかける形で行われ、対面式ではありません。
グローバルな活躍を目指して英語系の資格を取るなら、それぞれの試験の特徴を理解したうえで、自分に合ったものを選びましょう。
【PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)】世界中で認知された資格で、大きなアドバンテージとなる
PMP® 試験は、米国に本部があるPMIというNPO法人が実施している国際資格です。
プロジェクトマネジメント(期限の決まっているプロジェクトの計画や課題管理など、進行を管理する手法)に関する知識や経験を証明できるもので、IT業界や建設業界をはじめ、多くの業界から注目されている資格のひとつです。
ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー、経営コンサルタント、ビジネスアナリストといった職種では特に役立ちます。
受験資格があり、プロジェクトマネジメントの経験(高卒の人は5年、大卒の人は3年、院卒の人は2年)がある人、35時間の公式研修への参加が条件となります。
試験に合格した後も、継続的な教育や能力の育成のために、CCRと呼ばれるプログラムに従事する必要があり、更新手続きも必要です。
【USCPA(米国公認会計士)】国際的に知名度の高い資格で、グローバルなキャリア形成に役立つ
USCPAはアメリカの公認会計士資格で、国際的に知名度の高いビジネス資格です。
会計・税務のプロフェッショナルとして、日本を本拠地としたグローバル企業や外資系企業で活躍でき、海外事業部のある一般企業や金融機関、監査法人などに勤務する人もいます。
日本にも公認会計士資格はありますが、日本と海外では会計基準に違いがあるため、外資系企業などでは能力を十分に評価してもらえない場合があります。
USCPAなら日本国内のみならずグローバルなキャリア形成に役立てられます。
【介護福祉士】介護・福祉の求人は多く、取得しておくと有利になる
ヘルパーの仕事は高齢化社会の現代において不可欠で、貢献度が高いです。介護・福祉の求人は多く、今後も需要はますます高まると見られています。
介護・福祉系の資格は多くありますが、訪問介護を行うなら、雇用形態に関係なく「介護職員初任者研修」か上位資格の取得が必須です。介護職員初任者研修は誰でも受講でき、難易度も比較的低いので、挑戦しやすいです。
上位資格となるのは「介護福祉士実務者研修」です。介護分野で唯一の国家資格である「介護福祉士」の受験資格のひとつであり、ヘルパーを教育する「サービス提供責任者」に就ける資格でもあります。
介護福祉士には受験資格があるので、働きながら取得するには最短でも3年程度かかるといわれていますが、取得すると介護職への転職の際には有利で、資格手当が付くケースも多いです。
難易度が高いですが、介護業界でのキャリアアップには「ケアマネージャー(介護支援専門員)」もおすすめです。また、介護施設での事務やケアマネージャーをサポートする「介護事務」の資格も人気です。
【医療事務】女性に人気があり、働き口が多く自分に合った働き方ができる
医療事務は病院やクリニックで、受付や会計をしたりレセプト(診療報酬明細書)を作成したりする仕事です。診療科が異なっても求められるスキルは基本的に同じなので、働き口は多いです。
医療機関は好不況に影響されず多くの人が利用し、高齢化によってますます需要は高まっているので、資格があれば安定して働けるでしょう。
資格がなくても医療事務として働くことは可能ですが、資格があった方が有利です。資格には「医療事務検定試験」や「医療事務(医科)能力検定試験」など、いくつか種類があり難易度もさまざまですが、どれも就職や転職で役立ちます。
国家資格はなくすべて民間資格で、自分のレベルやスキルに合わせて取得できるでしょう。
【調剤薬局事務】取得しやすく、薬の専門知識がなくても合格を目指せる
調剤薬局事務は、調剤薬局で受付や会計、レセプトの作成、薬剤師のサポートなどをする仕事です。調剤薬局は全国各地にあるので、自宅の近くで働き口を見つけることも可能です。
資格がなくても調剤薬局事務の仕事はできますが、「調剤薬局事務資格」「調剤事務管理士」「調剤報酬請求事務専門士」などの資格を取得しておくと転職や再就職で有利です。
手に職をつけられる仕事でありながら、誰でも受験でき、比較的難易度が低いので取得しやすいです。薬の専門知識がない人でも合格を目指せるでしょう。
【登録販売者】薬局やドラッグストアで好条件で働ける
登録販売者は、薬剤師に次ぐ薬のスペシャリストです。薬局やドラッグストア、ホームセンター、スーパー、コンビニなどで、風邪薬や鎮痛剤など一般用医薬品を販売できるようになる専門の資格です。
薬局やドラッグストアの多くは、登録販売者の資格手当を設けていたり、時給を高く設定していたりするので、よりよい条件で働けるでしょう。
薬剤師は慢性的に不足しているので、登録販売者の需要は高いです。受験資格はなく誰でも受けられるので、社会人でも取得しやすい資格です。
【インテリアコーディネーター】まずは一次試験の合格を目指し、翌年以降に二次試験を受けることもできる
インテリアコーディネーターは、住まいのスペシャリストとして、お客様の要望を聞いてインテリアを提案し、快適な暮らしを提供する仕事です。
ショールーム、工務店、リフォーム会社、デザイン事務所、不動産会社などで有資格者が求められ、さまざまな場所で活躍できます。
女性に人気の民間資格で、インテリア関連の業界で働く人たちの合格率が高いですが、受験資格はなく誰でも挑戦できるので、インテリア、建築、デザインなどに興味のある人にはおすすめです。
難易度は比較的高く、一次試験ではインテリアの歴史、構造、環境、設備、インテリア関連の法規や制度など幅広い知識が問われ、二次試験には論文とプレゼンテーションがあります。
【保育士】将来性のある資格で、一度取得すれば一生使える
保育士資格を取得する方法には2種類あり、ひとつは厚生労働大臣が指定する大学や短大、専門学校を卒業する方法ですが、もうひとつは保育士試験を受験して合格する方法です。
社会人でも保育士試験に合格すれば保育士資格を取得でき、一度取得すれば生涯有効です。
受験資格がありますが、保育とまったく関係のない短大や大学を卒業していても受験資格があり、年齢制限もないので受けやすいでしょう。
保育士の有効求人倍率は高く、待機児童問題は解消されつつあるものの、保育士が足りない状況はまだまだ続いています。今後も需要がある将来性のある資格のひとつといえます。
保育士試験は年に2回実施されており、筆記試験9科目とすべてと実技試験3科目から2科目を選んで合格する必要があります。筆記試験の合格した科目は翌々年まで有効なのでチャレンジしやすいでしょう。
【秘書検定】社会人としてのマナーが身につくので、取得しておいて損はない
秘書検定は、社会人として身につけておきたいビジネスマナーや一般常識を身につけられる検定です。言葉づかい、電話応対、目上の人への接し方などをはじめ、オフィスの環境整備や文書のファイリングなど、実用的な技能も得られます。
秘書を目指す人や事務職では有利になる資格ですが、職種に関係なく社会人なら取っておいて損はないでしょう。
3級・2級・準1級・1級の4つがありますが、就職や転職でアピールできるのは2級以上です。秘書を目指すなら準1級もしくは1級の取得が求められることが多いです。
【ネイリスト】ネイルサロン以外にも活躍できる場所が多くある
ネイリストは、お客様の爪を手入れしたりデザインを施したりして、指先を美しく見せる仕事です。ネイリストになるために資格は必須ではないですが、取得しておく方が有利です。
ネイルサロンだけでなく、エステサロン、ブライダル業界、美容室などでも活躍でき、ネイリストの需要は今後も高まると見られています。自宅で開業するなど独立も可能な職業です。
ネイリストの資格には、「ネイリスト技能検定試験」「JNAジェルネイル技能検定試験」「ネイルサロン衛生管理士」などさまざまな試験がありますが、どれも民間資格で誰でも挑戦できます。
通信講座ならプロ仕様のネイルグッズがセットになったコースもあり、楽しみながら学べるでしょう。
ここまで27もの資格を紹介してきましたが、ほぼ網羅しているのが通信講座の「アガルートアカデミー」です。
フルカラーのわかりやすいテキストに加え、オンラインの講義動画があるので、インターネット環境さえあればいつでもどこでも受講できます。講義画面にはテキストが表示されるので、テキストを持ち歩かず外出先でも学習を進められます。
講師に質問できるサポート制度や、合格時のお祝い金や受講料の全額返金制度など、嬉しい制度が充実しています。
受講相談、資料請求、体験などはすべて無料です。担当がしっかりフォローしてくれるので、まずは相談して話を聞くだけでも価値があるといえますよ。
需要のある資格や男女別におすすめの資格は?

需要のある資格とは具体的にどのような資格なのでしょうか。また、男性におすすめの資格、女性におすすめの資格には何があるのでしょうか。
業務独占資格、IT系、介護福祉系などは需要が高い
業務独占資格とは、その資格がなければできない業務に携われる資格のことです。
紹介した資格の中では、社労士、行政書士、宅建士、管理業務主任者、電気工事士などが該当し、需要が高いです。
業務独占資格を持った人は常にニーズがあり不況にも強いです。「手に職をつけたい」「専門的な仕事がしたい」「独立や開業を目指したい」という人には、業務独占資格の取得がおすすめです。
また、将来性が高く、今後伸びると予想される業界に関連した資格は、需要が高いです。紹介した資格の中では、iパス、MOS、医療事務、介護福祉士、保育士などが該当します。
DXの推進やIT技術の向上によって、IT業界の人材の需要はますます高まっています。
IT業界の登竜門としておすすめのiパス、上位資格である基本情報技術者試験や応用情報技術者試験、MOSなどは、IT業界で活かせる資格です。
少子高齢化の現代において、医療系や介護系の資格も需要が高く、医療のIT化によって、IT知識を併せ持つ人材が求められるケースも増えています。
男性には安定した仕事に就きやすくなる資格がおすすめ
男性に人気のあるのは、業務独占資格や必置資格(設置義務資格)など、安定した仕事に就きやすくなる資格です。
業務独占資格については先述しましたが、必置資格とは有資格者の配置が法的に義務付けられている資格のことです。
業務独占資格は難易度の高いものが多いですが、専門性が高く独立や開業も可能で職に困ることはないでしょう。必置資格も安定した仕事に就きたいという人にとっては有力な選択肢となります。
女性には転職や勤務形態の変更に対応しやすい資格がおすすめ
キャリアアップや転職でアピールできる定番の資格は、日商簿記、FP、iパス、MOSなどです。手に職系なら、医療事務、調剤薬局事務、登録販売者などがおすすめです。
結婚、出産、引っ越しなどライフステージの変化に伴い、転職や勤務形態の変更を余儀なくされる女性は多いですが、そんなときでもこれらの資格があれば武器になるでしょう。
おすすめの資格はキャリア設計によって異なるので、まずはキャリアを設計し、どのような資格がぴったりか考えてから取得するとよいでしょう。
社会人が資格を取るメリットは多い
働きながら、毎日勉強の時間を確保するのは難しいものです。モチベーションを維持するのも簡単ではないので、資格を取りたいと思いながらも、なかなか踏み切れない…という人も多いでしょう。
しかし、社会人が資格を取得することには、以下のようなメリットがあります。
- 社内での評価がアップする
- 転職する際に有利になる
- 独立する際に有利になる
それぞれについて詳しく見てみましょう。
社内での評価がアップし、昇給や昇進につながる
1つめのメリットは、社内での評価アップが期待できることです。業務に関連した資格を取得することで、仕事に対する前向きな姿勢を示すことができ、任される仕事も増えるでしょう。
人事評価がアップすれば、給料アップにもつながる可能性が高いです。
企業によっては、基本給に加えて資格手当が支給されるなど、昇給や昇進につながります。一時金や補助金が支給され、資格取得にかかった費用が支給されることもあるでしょう。
キャリアの選択肢が広がり、転職の際に有利に働く
将来的な転職を視野に入れて資格を取得する人も多いかと思います。近年は年功序列ではなく、個人の能力を重視した評価が主流になっているので、資格は大きな武器となります。
資格を取得することでキャリアの選択肢が広がり、転職の際のアピール材料なるのはメリットのひとつです。資格があることで即戦力として期待してもらえるでしょう。
資格は専門知識やスキルをアピールできるだけでなく、意欲や向上心の高さも証明できます。資格を持っていないとできない仕事もあり、転職の応募条件に資格が必須とされている場合もあります。
客観的にスキルを証明でき、独立や開業を目指せる
将来的に独立や開業をしたいという目標があるなら、社労士や行政書士など独占業務のあるフリーランス向きの資格を取得することで、目標を叶えられるでしょう。
独立や開業をすれば、好きな時間に好きな場所で仕事ができ、頑張った分だけ売上が伸びるというメリットがあります。
ただし、独立や開業はすぐにできるわけではなく、実務試験や研修を経て登録をする必要があるので、開業に至るまでには一定の準備期間が必要です。
他にも、社会人が資格を取るメリットには、働きながら資格を取ることで収入が途絶えない、考え方や視野が広がる、教育訓練給付制度を利用できる、などがあります。教育訓練給付制度については後述します。
資格取得後の具体的なキャリアパスを設計しておこう
資格取得後のキャリアパスを具体的に描いておくと、資格取得に対するモチベーションがアップするでしょう。
キャリアパスは、「企画職に就くには、〇〇の資格を取得する必要がある」「〇〇の資格があればマネージャーになれる」など、企業がキャリアパス制度を明確にしている場合もありますが、自分で設計しなければいけないケースもあります。
キャリアパスの具体例を2つ紹介します。
例1. 人事部門で社労士資格を取得したら、管理職に昇進できた
社労士資格は、総務の業務内容を網羅的に身につけられ、特に人事部門が行う業務と関連性が高いです。企業からの人気が高い資格のひとつで、昇進や昇給の基準にしている企業は多いです。
社労士資格があれば、社会保険の加入・喪失をはじめ、傷病手当金や産休育休手当金の申請、労働保険料の計算ができるだけなく、従業員に対するハラスメント、解雇に伴うトラブル、ストレスチェックなど幅広い業務に対応できます。
人事部門で働きながら社労士資格を取得して管理職に昇進できた事例や、社労士資格を取得したことで総務や人事部門に移動や転職ができた事例があります。
社内でのキャリアアップはもちろん、フリーランスとして独立したり社労士事務所に転職したりと、さまざまなキャリアパスがあり、年収アップも期待できる資格です。
例2. FP資格を活かして独立開業したら、年収が2倍になった
FPの資格は、銀行や証券会社、保険会社など金融に関連する業界はもちろん、一般企業でも経理部門などでは昇進や昇給の対象になりやすいです。
また、FPの資格があれば、FPとして独立開業し、直接お客様の相談に乗ってアドバイスをすることが可能です。
FPとして年収1,000万円以上を目指すことも可能で、実際に年収が2倍に増えた人もいます。
独立するのであれば入念に準備をする必要があり、安定した収入を得るのは簡単ではありませんが、自分の裁量で仕事ができ年収アップを狙えるメリットは大きいでしょう。
自分の目指す将来像を明確にし、必要な資格を洗い出そう
キャリアパスを設計する際は、まず自分の現在の立ち位置(これまでの経験、強み・弱みなど)を客観的に分析し、目指したい将来像を明確にする必要があります。
5年後や10年後に、どのような立場になっていたいのか、どのようなスキルを持っていたいのかなどを明らかにすれば、実現に向けて必要な資格も明確になってくるはずです。
企業が取得を推進している資格や、取得するにあたって補助金が出る資格などは、優先して取るとよいでしょう。
社会人が資格を取得するためのポイントは?
働きながら資格を取得するために重要なのは、以下の3つです。
- 資格を取得する目的を明らかにして、試験に申し込む
- 無理のないスケジュールを組み、勉強の時間を決めておく
- 通信講座を利用する
「現職のままキャリアアップを目指したい」「転職したい」「独立したい」「趣味を深めたい」など、資格を取る目的は人それぞれでしょう。いつまでに取得したいのかという目標もあるはずです。
まずは目的や目標を明確にし、頑張ろうというモチベーションを維持することが大切です。社会人は勉強の時間を確保するのも難しいですが、目的や目標が明確でないとモチベーションの維持が難しいです。
先延ばしにしてしまう癖がある人は、とりあえず試験に申し込んでしまうのも方法のひとつです。
資格を取得するなら、勉強を習慣化する必要があります。スケジュールや勉強時間を決めずにその日の気分でやろうと思っても、徐々に面倒になって後回しにしてしまう可能性があります。
試験日まで無理のないスケジュールを立て、「毎週日曜日に2時間は勉強する」「通勤時間を勉強に使う」といったように勉強の時間を決めておくとよいでしょう。
また、社会人には独学よりも通信講座の利用がおすすめです。受講料が高いものもありますが、カリキュラムが組まれているので効率よく勉強でき、「お金を無駄にしないよう勉強を頑張ろう」というモチベーションにもつながります。
通信講座は自分のペースに合わせて学べるので、仕事の時間が不規則な人や家事や育児で毎日決まった時間を確保できない人にもおすすめです。
社会人には通信講座を利用した勉強法がおすすめ!
資格は市販のテキストを購入して独学でも取得可能ですが、通信講座なら効率よく勉強して合格を目指せます。
通信講座には、要点をおさえたわかりやすいテキスト、講義動画に加え、スマホ学習アプリなどもあるので、忙しい社会人におすすめです。
スマホを使って学習できれば、通勤や移動時間といったスキマ時間も有効活用できます。社会人におすすめの通信講座を5つ紹介します。
【アガルート】難易度の高い資格が豊富で、効率よく学習を進められる

アガルートアカデミーのおすすめポイントは、難易度の高い資格から低い資格まで豊富に取り扱っており、どれも高い合格実績を誇ることです。
行政書士、社労士、宅建士など国家資格の講座が多くあり、累計会員登録者数は17万人を突破しています。
フルカラーのわかりやすいテキストに加え、オンラインの講義動画があるので、インターネット環境さえあればいつでもどこでも受講できます。講義画面にはテキストが表示されるので、テキストを持ち歩かず外出先でも学習を進められます。
最小限の講義で合格できるよう、最良のテキスト×使いやすい受講環境で徹底的に合理化されているのが特徴です。
講師に質問ができるなどフォロー制度も充実しており、お祝い金もらえたり受講料が全額返金されたりする資格もあります。
【ユーキャン】100種類以上の講座があり、WEB学習にも対応している
生涯学習のユーキャンのおすすめポイントは、実用的な資格講座から趣味系の講座まで充実していることです。
社労士、行政書士、宅建士、簿記、FP、医療事務などの資格講座をはじめ、趣味の延長線上で気軽に学べる実用ボールペン字や整理収納アドバイザーなど、全部で100種類以上の講座があります。
オリジナルのテキスト以外に、DVDやWeb学習にも対応しているので、スキマ時間に講義動画を観たりデジタルテキストを使ったりして勉強できます。
「学びオンラインプラス」という専用のサポートサイトがあり、スケジュール管理やテストの受講、質問などができるので便利です。
【オンスク.JP】Web学習に特化していて、スキマ時間を使った学習に適している
オンスク.JPは、スマホでもPCを使って、いつでもどこでも動画や問題演習で学べる「Webの資格学習サービス」です。
おすすめポイントは、講義動画が1動画5分から視聴できるので、スキマ時間を使った学習に最適なことです。問題演習も一問一答形式なので、スキマ時間を活用できます。
講義動画では、専門用語はわかりやすく嚙み砕いて説明してくれ、しおり機能や倍速再生機能などもあるので、効果的に学習できます。
月額定額でいくつでも講座を受講できるプラン(ウケホーダイ)があるので、FP技能士×日商簿記、宅建士×インテリアコーディネーターなど、複数の講座を同時期に学ぶことも可能です。
【大原】ビジネス系資格に強く、自分に合った受講スタイルを選べる
資格の大原(社会人講座)は、通信講座だけでなく、教室通学や映像通学があり、自分に合った受講スタイルを選べるのが特徴です。
大原の学校は日本全国に48ヵ所あり、駅近くで通いやすいので、近くにお住まいの人は通学もおすすめです。
通信講座には、ライブ配信型のWeb講義、Web通信、DVD通信、資料通信など、ひとつの資格に対して複数の受講スタイルが用意されているので、ライフスタイルや予算に合わせて選べるでしょう。
資格の大原は、受講スタイルの多さ以外に、実績豊富な講師陣、合格のためのノウハウが満載のオリジナル教材、充実のフォロー体制などが特長です。
一発合格主義!をかかげ、ビジネス系資格は合格者数も圧倒的な多さです。社会人講座では、公認会計士や税理士など難関の資格でも合格者を多数輩出しています。
【ヒューマンアカデミー】250以上の講座から選べ、質問は何度でもできる
ヒューマンアカデミーの通信講座「たのまな」には、ビジネス系資格から趣味系講座まで約250の講座があります。
人気の資格講座は、医療事務、保育士、ネイリスト、登録販売者、宅建士などです。たのまな公式YouTubeチャンネルがあるので、自分に合った資格をみつけてみましょう。
ヒューマンアカデミーには、充実の学習サポート、質問無制限、無料延長制度、無料オンラインセミナー開催、開業・副業サポートという5つの特長があります。
学習サポートプラットフォーム「assist」では、自分だけの学習スケジュールを作成したり、講義動画を視聴したり、練習問題を解いたりできます。
各講座には受講期限が設けられていますが、1回限りで無料延長制度を利用することができます。オンラインセミナーが毎月開催されており、受講中の講座以外にも参加ができます。一部の講座では開業・副業の相談もできます。
資格を取るのにおすすめの制度を活用すれば、コストを抑えられる
通信講座には、教育訓練給付制度の対象となる講座があります。
教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して終了した場合に、支払った費用の一部が支給される制度です。
専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があり、通信講座は一般教育訓練に含まれます。一般教育訓練では、支払った受講料の20%(上限10万円)が給付されます。
社労士、行政書士、宅建士、日商簿記2級、FP、iパス、介護福祉士など多くの資格が対象です。給付の対象となる通信講座は厚生労働省のサイトに載っていますので、ご覧ください。
制度を利用できるのは、一定の雇用保険加入期間を満たしている人です。はじめての場合は受講開始の時点で雇用保険の加入期間が満1年以上、2回目以降は前回の受講から3年以上である必要があります。
市販のテキストを購入して独学すれば最低限の費用で済みますが、社会人なら教育訓練給付制度を利用することで通信講座の受講費を抑えられます。
社会人におすすめの資格に関するQ&A
社会人におすすめの資格について、よくある質問と答えをまとめましたので、参考にしてみてください。
Q.社会人が持っておいた方がいいおすすめの資格は?
A.ITパスポート(iパス)、マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)、TOEIC、秘書検定などは、業種・職種に関係なく、社会人におすすめの資格です。
金融業界ならファイナンシャルプランナー(FP)、不動産業界なら宅地建物取引士(宅建士)などもおすすめです。
Q.社会人の女性におすすめの資格は何?
A.日商簿記、FP、iパスなど定番の資格に加え、医療事務、調剤薬局事務、登録販売者、保育士、ネイリストなどがおすすめです。
自分のキャリアプランに応じた資格を取得しましょう。
Q.社会人の男性におすすめの資格は何?
A.社労士、行政書士、宅建士、中小企業診断士、電気工事士、危険物取扱者などがおすすめです。
業務独占資格や必置資格を取得しておくと、安定して働けるでしょう。
Q.高卒の社会人が取得できる資格はある?
A.学歴や実務経験に関係なく受験できる資格はたくさんあります。行政書士、宅建士、中小企業診断士、iパスなど、国家資格にも受験資格のないものが多くあります。
有用な資格を取ることで、大卒の無資格者より優位に立てるケースは珍しくありません。転職の際にも資格があることで学歴をカバーできる可能性は十分にあります。
Q.海外で働くときに使える資格は?
A.英語関連ならTOEFLやIELTS、経理・会計関連ならUSCPA(米国公認会計士)などが役立ちます。PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)やMOSなども世界で通用します。
海外勤務や海外留学を目指す人は、グローバル資格を取得しましょう。
通信講座を活用し、自分に役立つ資格を取ろう
社会人が資格を取ることには、社内での評価アップやキャリアアップなど多くのメリットがあります。
社会人におすすめの資格はたくさんあるので、自分のキャリアプランに応じた資格やこの先需要のある資格を選んで挑戦してみましょう。
まとまった勉強時間の確保は大変ですが、通信講座を活用すれば通勤時間やスキマ時間を利用して効率よく学習できます。
通信講座には教育訓練給付制度対象の講座があるので、コストを抑えられるのも魅力です。
合格をゴールにすることも大切ですが、自分のキャリアアップや新たな人生をイメージしながらコツコツと、資格取得に挑戦してみましょう。